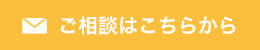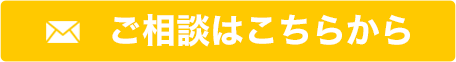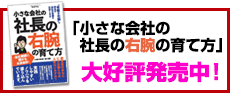多様性の裾野
2022年09月29日
株式会社ハッピーコンビの荒井幸之助です。
「多様性の時代」ということが一時期から言われてきました。
でも、「多様性」とは何でしょうか?
以下はウィキペディアからの引用です。
多様性(たようせい、英: diversity)とは、幅広く性質の異なる群が存在すること。
性質に類似性のある群が形成される点が特徴で、単純に「いろいろある」こととは異なる。
また、ウィキペディアでは、自然科学と社会科学では異なるとあります。
私たちが普段見聞きするのは社会科学的な概念のようです。
・社会科学や人文学では、多様性が社会の変化と発展に不可欠な要素とみられることがある。
・たとえば、グローバリゼーションなどにより、特定の文化や地域の持つ問題解決的発想の喪失などのデメリットが憂慮されることから、文化多様性・地域多様性などの概念が用いられている。
・価値観の多様性などの概念が用いられることもある。
これはインターネット、SNSの発達で、個人の考えが容易に人目に触れるようになったことが原因ではないか。
つまり、多様性の見える化が影響しているのではないでしょうか。
ネット上の個々の情報は、似たもの同士の意見という群を作る。
これまでは見えなかった群が現れる。
そしてその群が大きくなり、社会での存在感を増す。
多様性の本質は、リアルな世界に「ネットの世界」が生まれたことなのかも。
私たちの暮らしのすぐそこに、リアルでは発現しない価値観が飛び交う世界ができた。
ネットの世界はビジネスの宝庫です。
新しいことがどんどん簡単に創れて試せます。
誰でも参加しやすいです。
メタバースの世界など、商業利用をつうじて今後も拡大していくのでしょう。
多様性の世界を支配するについて、ビジネス界では熾烈な競争が行われています。
私たちは、仕事や学校での活動がオンラインで代替できることに気づきました。
こうした世界がどんどんバーチャルで展開されていく。
特に移動の概念は、その目的も含めてこれから大きく変わるのではないでしょうか。
こうしてネットの世界が多様化すれば、リアル住民との考え方の差は大きくなると思います。
同じ国でも、隣の住人は全く理解できない、なんてことが当たり前になるということです。
ネットメディアの存在感が増せば、マスメディアの影響力はどんどん低下していくでしょう。
マスメディアしか見ない人とネットの世界の住人は、更に互いを理解できなくなる。
世界はこうして多様性の名の下に分断されていくように思えてなりません。
でも、それを新たなビジネスチャンスと考える。
そのためには、ネット世界の住人の価値観を理解することが必要です。
今後ますますネットによる多様性の裾野が広がる時代。
すぐそこにある新たな世界に旅立つ勇気が求められるのではないでしょうか。